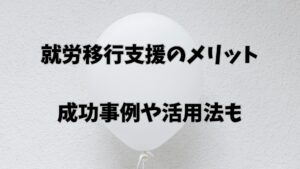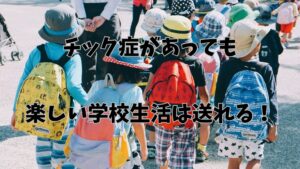- 自分にはチックがあるけど他のチックをもった人はどんな症状があるんだろう?
- 成長していくと症状はどう変化するの?
- 子供がチックだけど無事大人になって働けるんだろうか?
自分や家族にチックがあると、こういう悩みをもちますよね。
僕ははるといいます。3歳の頃からチックがあり、それから29年間チック症を患っています。
発達障害、強迫性障害や双極性障害などの合併症がありながらも、福祉就労、就労移行支援を利用したり、障害者雇用で働いたりしてきました。
この記事では、僕が今までにでたチックの症状、チック症とうまく付き合うために実践したことなどをお伝えします。
他人のチック症状を知ることで、チックで困っているのは自分だけじゃないんだと思っていただけたら幸いです。
チック症とは
最初にチック症とは何なのか説明します。
もうすでに知っているという方は次の「今までにでたチック一覧」から読んで下さい。
チック症とは、本人の意思とは関係なく突然体が動いたり声がでたりする疾患です。
チック症には運動チックと音声チックがあります。
一時的に治まることもありますが、ストレスや疲れで悪化する場合があります。

さらにチックには、複雑運動チックと複雑音声チックがあります。
どちらも状況や会話の文脈に合わないタイミングで起こるため、周りの人に誤解されやすいです。
複数の運動チックと1つ以上の音声チックが1年以上続くものをトゥレット症候群と呼びます。神経発達症(発達障害)に分類される疾患です。
チックは知ってるけど、トゥレットは初めて知ったという方もいるでしょう。
最近はYouTubeでもトゥレット症候群についての動画が増えました。当事者の方を取材した動画、当事者自身が発信している動画などさまざまです。
僕もトゥレット症候群と診断されています。トゥレット歴は長いので、僕の経験をあなたのこれからの人生に、少しでも役立てられたらなと思っています。
今までにでたチック一覧


ここからは、僕が3歳だった頃から今の32歳までにでたチックの症状を時系列でお伝えします。
- 最初はクセのような単純チックだった
- 小学生の時のチック
- 中学生の時のチック
- 高校生の時のチック
- 大学生の時のチック
- 社会人になってからのチック
- 現在のチックの症状
こんな風にチックは移り変わることもあるんだと、数あるチック症の変化の中の1つの事例として見ていただけますと幸いです。
あなたやあなたの家族より症状が軽い面、重い面があると思いますが、あなたの経験と比べながら読んでみてください。
最初はクセのような単純チックだった
母から聞いた話ですが、僕に最初のチックが見られたのは3歳の頃だったようです。
瞬きと首を横に傾ける運動チックが始まりでした。



チックの知識がなかった母は、クセかな?と思っていたようです。
しだいに音声チックが始まり、「ウッ、ウッ」と言ったり豚の鳴き真似のようなチックがでてきました。
小学生の時のチック


運動チックは、首振り、顔しかめ、ジャンプが新たに加わりました。
音声チックは、「ウッ」「アッ」と突発的にでて、声のボリュームがだんだん大きくなってきました。
小学生の頃から、単純運動チック(突発的な動きのチック)だけではなくて、複雑運動チックもでてくることに。
顔をしかめる、ジャンプなどは複雑運動チックに分類されます。
大人になってから母に聞いたのですが、小学3年生時の担任の先生が、職員会議でほかの先生に対し、僕(筆者)のチックの症状はわざとじゃないから怒らないでくれと伝えていてくれたようです。当時の担任の先生には感謝の気持ちでいっぱいです。



ほかの先生たちに伝えてくれていたからチックを注意されることがなかったのかと、今振り返ると思います。
小学生の時のチックについて詳しくはこちらの記事で解説しています。
»チック症の小学生の困りごと
中学生の時のチック
運動チックは、口をとがらせる、つい手を触れてしまうチックが仲間入り。
音声チックは、「ウッ」「アッ」に加えて「クサッ」というのがでるようになりました。
音声チックのピークは中学時代でした。
中学校までのチック症を振り返ると、クラス替えや受験など変化が多い時に症状がひどくなっていたと感じます。
中学3年時が特に音声チックが酷かったので、からかったりしてこなかった当時のクラスメイトには本当に感謝です。
小学校時代からの良い友人関係や担任の先生たちの計らいに恵まれたこともあり、小中学校はイジメや大きな問題なく過ごせました。
中学生の時のチックについて詳しくはこちら
»チック症の中学生の困りごと
高校生の時のチック


高校ではクラスのほとんどが知らない生徒ばかりでした。新しい友達に変に思われないように、音声チックがでるのをめちゃくちゃ我慢しました。



そしたら、悲しいかな、音声チックを抑えすぎた反動か運動チックがひどくなってしまいました。
体がビクつくチックが出現しました。高校では運動チックのピークで、この体がビクつくチックに翻弄されます。
高校時代は、クラスメイトに陰口を言われたりチックのマネをされているのを、何度も目撃しました。
思春期で他人の目に敏感だった僕は、それがとてもショックで。「ヤバい、チックをだしたらまた言われる。」と恐怖を感じ、その場で固まっていました。チックの悪口を言われているのが分かる度に、顔が熱〜くなって、とても恥ずかしかったです。
他校の生徒と合同で模試があった時には、僕の側の生徒に、僕に聞こえるくらいの声で「マジでうるせぇ」と言われたこともありました。
とてもじゃないけどその生徒の方を見れなかったです。
高校では体が震えるチックに加え、強迫症状が強くなったり、コミュニケーションが苦手だったりしたこともあり、クラスメイトからは奇異な目で見られていました。
ここで、強迫症状について説明します。
強迫症状でプリントを何回も触ったり、机やバッグから教科書を何回もでし入れしたり、何十分も体がフリーズしたりしていました。
さらにはうつ症状もありました。気分の落ち込みやボーっと一点を見つめることが多くなったり、身だしなみを整えることもまともにできず、ロッカーはプリントでギュウギュウ詰めになっていました。
理由も知らない周りからは本当に変な奴として映っていたことでしょう。



チックに加え、強迫症状が本格的に始まった高校生の頃からが人生で1番辛い時期でした。
高校生の時のチックについて詳しく解説した記事はこちら
(近日公開)
大学生の時のチック
辛い高校生活を終えて、なんとか大学に進学できた僕ですが、相変わらず、チックも強迫症状も続いていました。
運動チックは、体や腕のビクつきがメインでした。
高校時代に我慢していた反動か、音声チックは、特定の言葉を繰り返す複雑音声チックがメインになりました。”頭の中に浮かんだ歌手の名前を10回言う”のような、マイルールに従って音声チックがでていました。トゥレットと強迫症状が絡み合った症状だったんじゃないかと分析しています。
強迫性障害(OCD)を対処する事も重要ートゥレット当事者会
チック障害との関連によるOCDの検討ー第104回日本精神神経学会総会
大学に入学してからも、強迫症状は日に日に強くなっていきました。
何時間も同じ場所で強迫行動と闘いつづけ、一晩中動けないことも多々あり、一番ひどい時で三日三晩ほとんど動けないことさえありました。



同じ考えが頭の中を巡り続けて、フリーズし自由に動けずにいたこの頃は、毎日ホントに泣きたいくらい辛かったです。
あまりの症状のおかしさに大学3年目の時、両親は僕を精神科に連れて行ってくれました。
精神科では困りごとを聞いてもらい、薬をだしてもらいました。薬の名前はあえて伏せます。どんな薬が合うかは人によって違いますので。
投薬が開始して1週間ほどで、強迫症状はウソのように軽くなりました。
薬のおかげで、チックもある程度は治まるようになりました。
自分の中では全くでなくなったと思ってましたが、主治医からは「でてるよ」と言われて、そうなのかと気づきました。
早く精神科にかかっていればこんなに辛い思いをせずに済んだのかなと、今では思います。あなたも少しでも心が辛いと思ったら精神科のドアをノックしていいんです。
大学の方はというと、取得単位が足りずに留年することになりました。
しかし、投薬のおかげで元気を取り戻せた僕は、大学4年目、5年目はフル単位を取得することができました。
投薬後、在学中にできた彼女は今の妻で、トゥレット症や強迫症状を理解してくれています。妻には感謝してもしきれません。本当にありがたいことです。
大学3年生の時の精神科通院が僕の人生のターニングポイントでした。
そして5年かかりましたが、無事大学を卒業することができました。
大学生の時のチックについて解説した記事はこちら
(近日公開)
社会人になってからのチック


大学在学中は単位を取って卒業することを第一目標にしていました。
企業の合同説明会に行くなど就職活動もしていましたが、発達特性もありうまく就活を進められず、就職先が決まらないまま卒業しました。
新卒カードを無駄にしてしまったのはとてももったいなかったです。
卒業後、運動チックは首振り、顔しかめ、体のビクつき、腰を突きだす動作がメインになりました。
音声チックは、「ニャニャッ」「クサッ」、テレビや話し相手から聞いた言葉を繰り返すのがメインになりました。
「クサッ」というチックは中学生ぶりにでるようになりました。僕のように、昔でていたチックが時を経て再びでることは珍しくないようです。
卒業後は約半年間、公務員を目指し勉強をしていました。
しかしその途中、精神科で自分には発達障害があると分かり、自分の進むべき進路を見直しました。
就職先を探している途中、障害者就業・生活支援センターという支援施設を知ることに。支援センターでは生活の困りごとや就職について相談することができました。
相談する中で、A型事業所なるものがあるのを知りました。
A型事業所とは?
A型事業所は法律に基づく福祉サービスの1つで、心身に障害をもつ人が利用できる就労形態です。
作業所と呼ばれることもありますが、正式には就労支援施設です。
A型事業所の特徴は、雇用契約を結ぶため最低賃金が保証されていること。一般企業での就労が難しい人が、福祉サポートを受けながら働けます。働きながらスキルを身につけ、一般就労を目指します。
A型事業所には、数日間お仕事体験をした後、面接を経て就職します。
僕はこれまで3社体験して、内1社に就職しました。就職先の事業所はPCや軽作業系のお仕事でした。
A型事業所で働く際にもチックはでていましたが、面接時にあらかじめ症状について説明していたため、過度に不安になることはありませんでした。
後から同じ職場の人から聞いた話では、聴覚過敏の他の利用者の方が僕のチックを気にしていたようでした。さまざまな疾患をもった人が働くため仕方ありません。



仕方ないのですが、その方には申し訳ない気持ちになりました。
そのA型事業所は仕事内容の変化や体調の悪化で、結局1年で辞めました。
A型を辞めた後、就労移行支援を利用しました。
就労移行支援とは?
就労移行支援も障害福祉サービスの1つで、障害や難病を抱える方などが一般企業への就職を目指すために必要な知識・スキルを習得する制度です。就職後も職場に定着できるよう支援してくれます。
2年間の利用上限があることには注意です。
主なサービス内容
・ビジネスマナーやPCスキル向上などの就労トレーニング
・書類作成や面接対策などの就職活動サポート
・職場見学・実習
・就職後の相談対応や環境調整をする職場定着支援
就労移行支援について解説した記事はこちらです。
»就労移行支援の利用方法(近日公開)
僕が利用したのは、PC作業系の就労移行支援事業所でした。
在籍中に数社の企業に応募しましたが、書類面接が通らず、結局就職できずに利用期間を終えました。
就労移行支援の利用で得られたことは、在宅就労での働き方に慣れたことと、タイピングが速くなったことくらいです。



20代というキャリアにおいて大切な時期を数年単位で使い、成果が得られなかったのはすごくもったいなかったです。
あなたには同じ失敗をしてほしくありません。
就労移行支援を利用する際に意識すべきことをまとめたこちらの記事を読んでみてください。
»就労移行支援を無駄にしないためにすべきこと(近日公開)
そして就労移行支援利用後は、障害者職業センターを利用して就職先を探しました。
あなたの住んでいる地域で検索してみると、障害者職業センターが見つかるはずです。
企業探しはハローワークとindeedという求人サイトを使って行いました。
結果的にIndeedの求人から企業に応募しました。
»仕事探しはハローワークよりIndeedなどの求人サイトがオススメな理由(近日公開)
僕はA型事業所を2社体験し、障害者雇用を1社受けました。
体験したA型の内1社は作業内容が合わず、もう1社は体験後に落ちてしまうことに。
正直、A型でも落ちることがあるのかと驚きでした。
その後応募したPC作業系の会社に障害者雇用で入社することに。面接の際には精神疾患のことを説明しました。
初めての一般就職ということもあり、緊張しました。
上司や一緒に働く同僚、就職後に繋がったジョブコーチ(職場定着を支援する専門職)の方々がとても良い方ばかりで、大きな問題を起こすことなく働けました。
チックは普通に出ていたのですが、誰からも悪く言われることはありませんでした。高校の頃からすると、こんなにチックを気にせず働けるなんて夢のようです。本当に周りの人たちに恵まれていたと思います。
しかし結局、在職中に気分の落ち込みがひどくなり、さらには難病も見つかり、1年で退職しました。



ただ、一般就労した経験は貴重でした。
働く大人のチック症に関する記事はこちらです。
»【大人のチック症】働く上でのチックの困りごと(近日公開)
現在のチックの症状
そして現在は、運動チックは顔しかめ、首振り、体や腕のビクつきがメインです。
音声チックは「クサッ」「ニャニャッ」「アッオー」、ミッキーマウスの声マネ「ハハッ」、聞いたり読んだりした言葉を繰り返す症状がメイン。
症状こそあるものの我慢できる時間は長くなり、チックの頻度もピークの頃とは比べ物にならないくらい低いです。
今でもチックの症状がでると、周りから見られるので少し気にはなります。
子供の保育園の発表会では、他の保護者から陰口を言われることもありました。
しかし、妻が理解者となってくれているおかげで、あまり落ち込まずにいられています。とても心強いです。
»恋愛でのチックの困りごと(近日公開)
»結婚・子育てでのチックの困りごと(近日公開)
チックの増減に影響を与えた要因


チックの症状の増減に大きな影響を与えたと感じた要因は次の2つです。
自分が置かれている環境の変化が激しいこと
精神科の薬を服薬したこと
順番に解説します。
自分が置かれている環境の変化が激しいこと
幼い頃から今まで、いろんな環境の変化がありました。
中でも変化が激しかったと思う時は以下です。
- 学年が変わってクラス替えがあった時
- 受験シーズン
- 進学した時
- 就活時期
- 社会人として働き始めた時
- 転職した時
こういった変化の多い時期に、自分のチックの症状は種類が変化したり、頻発したりしていました。
ですので環境が変化した時は、チックの症状の変化に気を配っています。
気を配るようになったのは、チックの増減をいつもそばで見ていた母から、「あなたは環境の変化がある時にチックがひどくなる」と教えてもらったのがきっかけでした。



あなたやあなたのお子さんも、チックがひどくなるのは環境の変化が激しい時なのではないでしょうか。
精神科の薬を服薬したこと
逆にチックが減ったきっかけもありました。
ぜんぜん意外ではないのですが、精神科の薬を服薬し始めたことです。
僕は21歳で初めてチック症に効く薬を飲み始めました。飲み始めの頃は薬に対してまったく期待していませんでした。
しかし、当時付き合いが長かった友人からも、「最近症状あまりでなくなったね」と言われるくらいにはチックが減りました。
誰にでも効くかと言われれば違うと思いますが、長引くチックで困っている方は一度精神科に通ってみるといいかもしれません。
チック症状がでた時の周囲の反応と対処法
チックがでて周囲から注意を受けた時の対処法は次の2つです。
きちんと自分の口で症状について説明すること
これが自分なんだと受け入れ、自分は自分の味方でいること
チックが出た時の周囲の反応を交えながら、この対処法をどんな時に使えばいいか解説します。
母と父の反応
僕の1番の救いは母がチックの症状に理解があったことです。
僕が小学生の頃、母は自分でチック症・トゥレット症について調べたり周りに聞いたりして、病院に連れて行ってくれました。
まだスマホも普及しておらず、インターネット検索も一般的ではなかった時代に、未知の病気を調べるのは大変なことです。
病院で僕の症状はやはりチックだったと分かりました。



当時僕を診てくれたお医者さんは、「時間が経てば自然に治る」と言っていたそうです。
多くの人はチックがでても一過性で終わるそうですが、僕の場合は違っていました。
早めに服薬できていたらもう少し楽だったのかな、なんて考えたりもしました。
今はチック症やトゥレット症について、テレビやYouTubeなどである程度広まったこともあり、我が子に症状が現れたら早めに精神科にかかれる人も多いでしょう。
万人に薬が効くとは思っていませんが、服薬を選択肢の1つとしてもっておくと安心ですね。
一方、父はというと、母とは対照的でした。
チックを指摘したり、マネしたり、バカにしたりしてきました。今となっては恨んだりなどはしていませんが、当時はものすごく嫌な気持ちになっていました。
だって勝手にでるんですから。止めろと言われても止められないのがチック症です。
こういう時に自分の口で症状を説明できたら、父も理解してくれたかもしれません。
友人の反応
高校が一緒になった、小学生から親しかったある友人からは、「震えんな」とたびたび注意されていました。
それまでに自分のことを知らない人から言われるならまだ分かります。実際に部活の先輩や同学年からも注意されていました。
それが付き合いが長い人からいまさら、周りの人たちと一緒になって「震えんな」?書いてて腹が立ってきました笑
当時は僕にトゥレットの知識がなく、注意されても止められないので、仕方なく黙ることしかできませんでした。
けれど今なら言えます。「チック症という病気のせいで、勝手に体が動いたり声がでたりするんだ」と。
あなたもいざという時のために、チックの説明をする練習をするのをオススメします。
高校のクラスメイトからは陰口の対象にもなりました。高校生の時期というのは多感ですので、陰口、本当に辛かったです。
この苦い経験のおかげで、今では就職面接の時はきちんとチックの症状を説明できています。
働く時も周りからなにか言われることなく仕事ができていました。でもやっぱり、心の中ではどう思ってるんだろうと、チックがでると周りの目を気にして疲れてしまいます。
23歳の時に主治医から自分はトゥレット症だと告げられてからは、これが自分だと受け止め、以前ほどチックを気にしないようになりました。
簡単そうに見えて難しいですが、あなたも心がけてみてください。
チック症とうまく付き合うために実践したこと


僕がチック症とうまく付き合うために実践したことは次の2つです。
目立つチックをだせない時は他のチックを代わりにだす
ストレスがかかっていると感じた時は外部からの刺激を少なくする
目立つチックをだせない時は他のチックを代わりにだす
生活する中で、体が震えたり大きな声をだしたりがどうしてもできない場面がありますよね。
我慢できる内は我慢しておいて良いのですが、すぐに限界がくるはずです。
そんな時に僕は、顔をわざとしかめたり小さな声をわざとだしたりします。
あなたも知らず知らずの内にやっているかもしれませんが、もし意識していないならば意識してやってみてください。
このチック置き換え法を「ハビットリバーサル」と呼びます。



無意識にやっていたことにまさか名前があったなんて!
ストレスがかかっていると感じた時は外部からの刺激を少なくする
チックってストレス下ででやすいのは皆さんご存知だと思います。
日常でストレスがかかっているなと感じた時は、深呼吸したり目をつむったりして外部からの刺激を少なくしましょう。
すると、幾分かチックの症状が和らぐことがあります。
チックがない人でも落ち着きますよね。
これからのチックとの向き合い方
これまで、10代の頃にでていた音声チックが20代前半で再びでたり、新たなチックがでたりしました。
これからもチック症は良くなったり悪くなったりを繰り返すんだろうなと思います。
しかし全体的なチックの頻度は、年齢を重ねていくにつれてだんだん低くなっています。
チック症であることは僕やあなたの一部です。チック症であることは僕やあなたの全てではありません。



チックがあっても臆することなく堂々と過ごしていきましょう。
まとめ
僕と同じように、運動チックや音声チックが子供の時からあり、大人になった現在もチックの症状で困っている方は少なくないと思います。
そんな同じ悩みをもつ方々とブログやTwitterを通して繋がれたら嬉しいです。
あなたは1人じゃありません。
これから定期的にブログ更新、ツイートしていきますので、コメントや返信などしていただけたら心から喜びます。
最後まで読んでくださりありがとうございました。